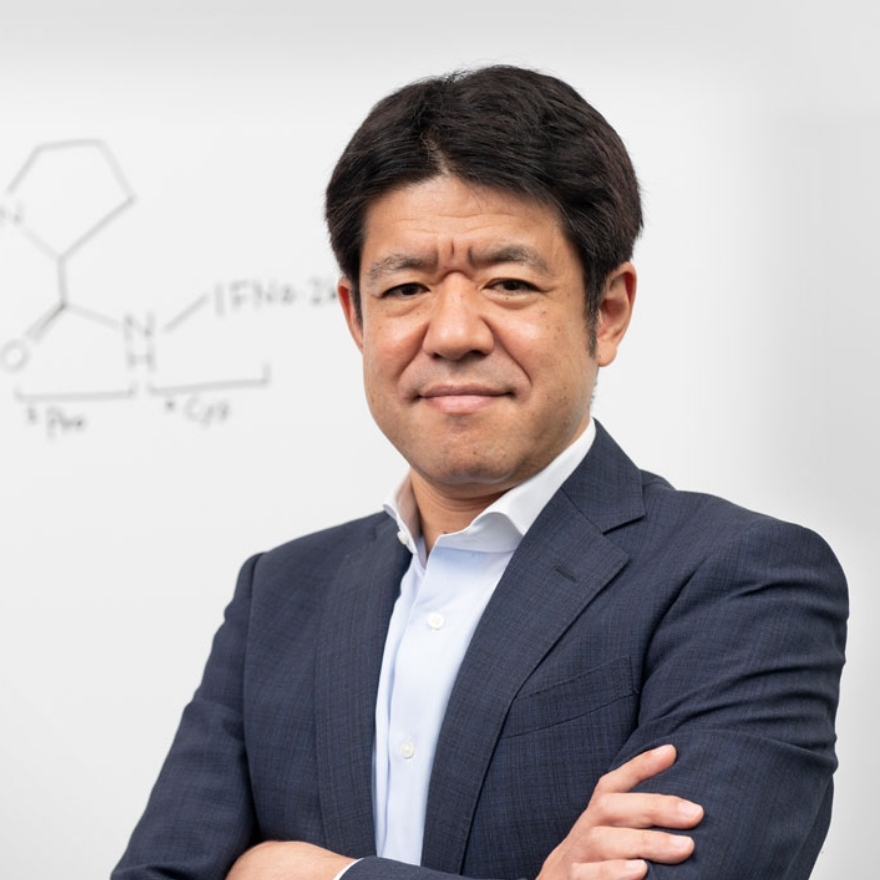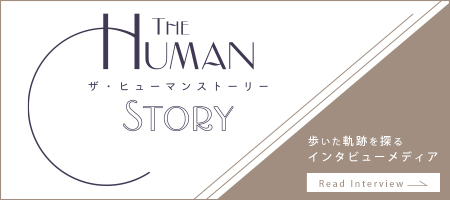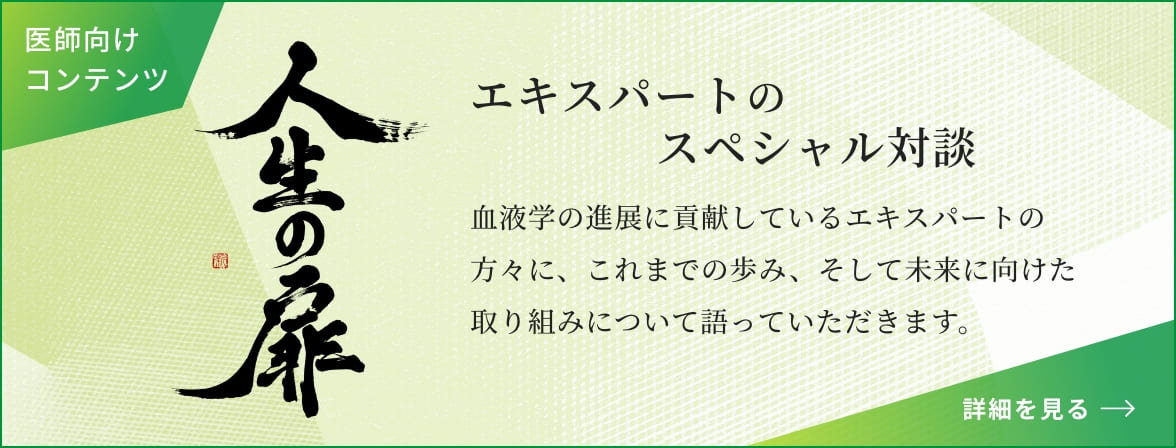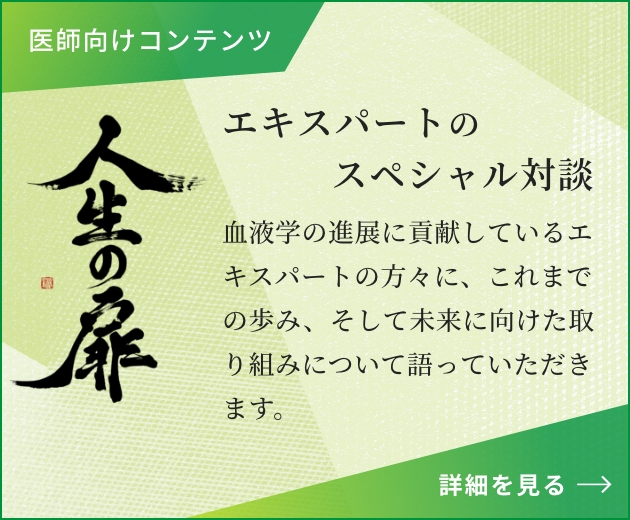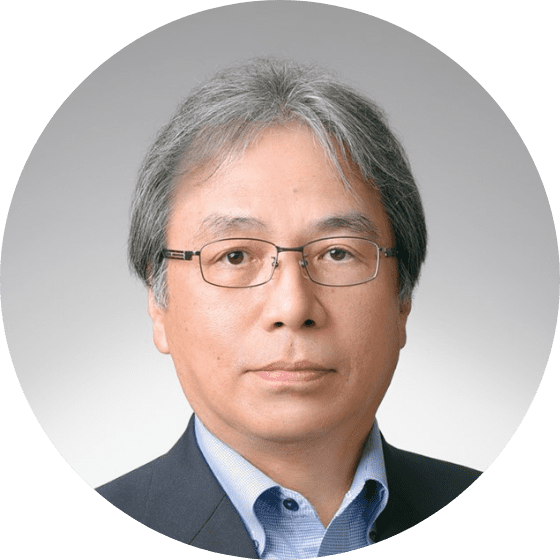社長メッセージ
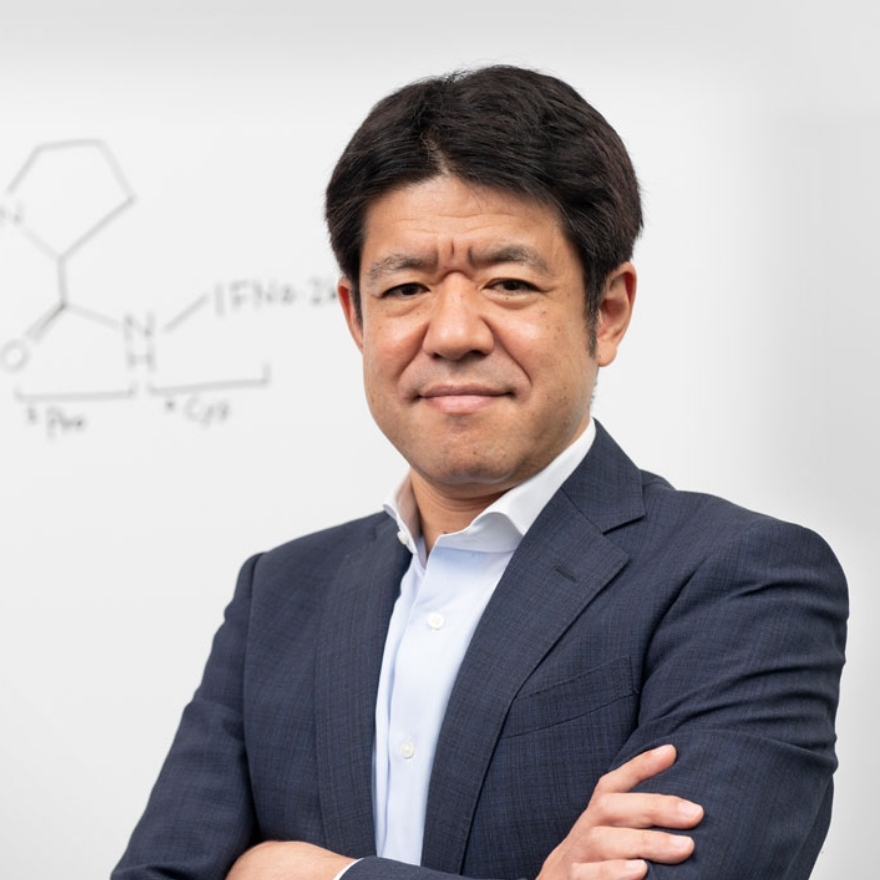
ファーマエッセンシアジャパン 株式会社
代表取締役社長
米津 克也
1971年生まれ 滋賀県大津市出身。
1995年山之内製薬(現アステラス製薬)入社、以後ヤンセンファーマ、ノバルティスファーマ、シャイアージャパンにて主に医療用医薬品のマーケティング職を経験し、2017年3月より現職。学生・社会人を通じてボート競技に勤しみ、チームワーク、リーダーシップを学ぶ。
学歴:英国国立ウェールズ大学経営大学院卒業(MBA) 、高知大学理学部卒業(生物学)。
「患者の声にどうこたえるか。」と「バイオテックカンパニーとして成長し続けること。」の両立。
この答えを出すことも、私たちの挑戦です。
「患者志向」「患者ファースト」とは、私たち製薬会社が生命関連企業である限り掲げなければならない理念・ミッションです。しかし、私自身が長年、製薬業界に身を置く中で、「本当に自分は患者さんに寄り添えているのか」、「医療に貢献できているのか」と自問することが、数多くありました。その背景として、組織が大きくなる中で役割が細分化されていき、患者さんや医療従事者との間に距離ができてしまうこと、また、ステークホルダーが増えることで意思決定にかかわる要素が多様化し、「患者さんのニーズに真に応えられているのか」が見えにくくなることがあると考えています。
バイオテックカンパニーとして、成長を目指しながら患者ファーストであり続ける。その両立は決して困難であってはならない。そう思います。これは、決して私一人の想いではありません。もっと患者さんと寄り添い、患者さんと同じ方向を向いて仕事がしたい。もっと医療に貢献したい。そう思い続け、その実現のために集った、ファーマエッセンシア社員全員の想いなのです。企業としてどんなに大きくなっても、社員が患者さんや医療従事者と同じ目線に立てること、「患者の声にどうこたえるか。」が社員の働く目的であり続けること、そして、会社の意思決定も常に「患者の声にどうこたえるか。」を基準にして行うこと。これらを企業文化としてしっかりと根付かせることで、私たちが目指す製薬会社の姿へと近づいていく。そう強く信じています。
さらに、医療や製薬を取り巻く社会的な問題にもアプローチできたら、と考えています。医薬品は情報を伴って初めて本来の機能を発揮します。薬を創り出すことに加え、薬の情報を広く正しく伝えていくことも、私たち製薬会社の大切な役割です。しかし実際には、専門性の高い医薬品の情報を患者さんに的確に伝えていくことは難しく、情報格差が生まれてしまっています。製薬会社サイドから社会にアプローチして、患者さん自身が自分にあった治療法や処方薬の選択に積極的にかかわることのできる世の中にしていきたい、と願っています。とても大胆な目標かもしれませんが、思い続け歩み続ければ、きっと実現できるはずです。「患者の声にどうこたえるか。」これこそがファーマエッセンシアの存在意義であり、未来に向けた約束です。
取締役 特別医学顧問メッセージ

医療関係者の方々、そして製薬業界を志す皆さまへ
新しい出会いこそが、夢につながる未来の扉を開くのです。
2021年4月、私は順天堂大学血液内科教授を退職し、ファーマエッセンシアジャパンの会長に就任しました。40年ほどの月日を大学病院の血液内科医として歩んできた私が、創業してまもない製薬会社の一員となったことに、驚かれた方も多かったようです。私自身、「定年退職したら製薬会社を立ち上げよう」などと考えていたわけではなかったのです。
私は血液内科医として臨床に携わる傍ら、骨髄増殖性腫瘍(MPN)の研究に取り組んできました。誰も明らかにしていないことを明らかにするという研究の魅力に取り憑かれ、MPNの発症メカニズムを解明した研究では、最終的にベルツ賞や日本血液学会賞を受賞しました。一方で、患者会の医学顧問を引き受けたのをきっかけに、臨床以外の場でもMPNの患者さんとかかわってきました。完治できる治療法がない中、患者さんは、いつか病気が進行し白血病になるのではないか、という不安と日々闘っています。「一刻も早く新しい良い薬ができてほしい」。そんな患者さんの声に応えられないか、考え続けていたのです。
そんな時、海外の学会でファーマエッセンシアの新たなMPN治療薬に出会い、「この薬をぜひ日本に導入したい――」と強く思いました。そのために、製薬会社という新しい世界に飛び込むことに迷いはありませんでした。
ここまでの道のりは私にとってごく自然な流れでしたが、思い返せば人生のターニングポイントには、必ずいろいろな人との出会いがありました。憧れていた宇宙工学ではなく医学を学ぼうと決めた時も、学生時代は苦手と感じていた血液学を専門にしようと決めた時も、思いがけない人との出会いがあり、それが私を新しい道へと導いてくれました。
だからこそ、これから医療や製薬業界を志す若い人は、失敗を恐れずチャレンジしてほしい。せっかく生まれてきたのだから、自分らしい人生を目指してほしいと思います。私もこれまで失敗はありましたが、そこでのチャレンジが人生の扉を開いてくれました。そして、なによりも、「生命」という最も大切なものに携わることができた。これは本当に素晴らしいことだと思っています。
「生命」に携わる誇りを持ちながら、患者さんに明るい未来を提供し続ける会社をつくっていくこと。それがファーマエッセンシアジャパンの会長として、私がこれからチャレンジしていきたい仕事なのです。
ファーマエッセンシアジャパン株式会社 取締役 特別医学顧問
順天堂大学 医学部内科学血液学講座特任教授
小松 則夫
1955年生まれ 茨城県石岡市出身。
1981年3月に新潟大学医学部卒業後、自治医科大学血液科病院助手を経て、1990年3月よりニューヨーク血液センター留学。1992年10月より自治医科大学内科学講座血液学部門(旧血液科)講師、助教授を経て、2004年10月に山梨大学医学部血液内科教授に就任。2009年8月より順天堂大学医学部内科学血液学講座主任教授(~2021年3月)。骨髄増殖性腫瘍(MPN)に関わる研究で2019年度第56回ベルツ賞、2020年度第9回日本血液学会賞を受賞。
2021年4月にファーマエッセンシアジャパン株式会社代表取締役会長に就任。2023年4月、取締役会長特別医学顧問に就任。
医薬品臨床開発を指揮・指導すると共に、主に血液内科医を対象とした医師向け学術対談プログラム「人生の扉」を運営配信。
Management Team
-
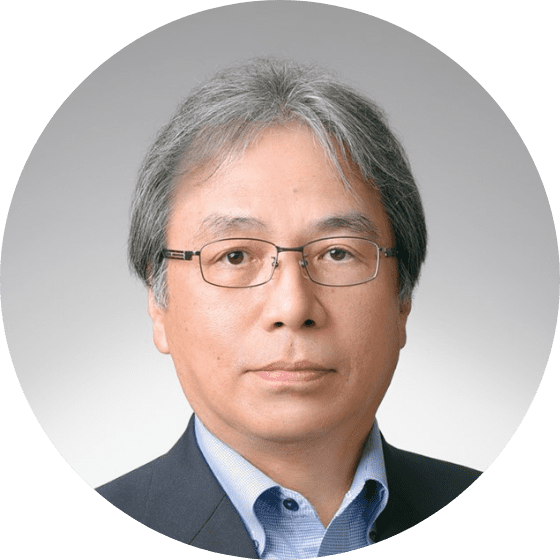
取締役副社長 グローバルクリニカルスタディー
ディレクター兼 R&D本部 本部長
佐藤 俊明
私は国立大学医学部で教壇に立ちながら研究者としてBasic Science Researchに没頭した後、心機一転して外資系製薬会社に転職しました。そこでは臨床試験を実施する部門を統括して数多くの医薬品の販売承認を取得してきましたが、医薬品開発は想像以上に厳しいものであり、常にチャレンジと変革が求められます。私はPatient Orientedを常にモチベーションとすることで困難を乗り越え歩み続けてきました。私にとってファーマエッセンシアが2社目の製薬会社になります。患者さんに一日でも早く医薬品を届けるために努力を惜しまない医薬品開発の原点が、この会社にあることを実感しています。
-

メディカルアフェアーズ本部 本部長
田中 智之
私は、診療・基礎研究・創薬・臨床開発・メディカルアフェアーズという複数の領域にわたり、25年以上にわたりキャリアを重ねてまいりました。特に抗体医薬品、血液・腫瘍領域および希少疾患領域においては、アカデミアと製薬企業の双方で、新規治療法の創出や臨床開発を主導してきました。国内外の医療現場と対話しながら、革新を現場のニーズと結びつけることを常に意識しています。
ファーマエッセンシアジャパンのメディカルアフェアーズ本部は、患者さん中心の視点を軸に、医療従事者との対話を通じて、真に価値ある医薬品情報の提供と、質の高い医療の実現に貢献していきたいと考えています。
「医療の未来を、共に創る」。その思いを胸に、一人でも多くの患者さんに希望を届けられるよう、チーム一丸となって挑戦を続けてまいります。
-

コマーシャル本部 本部長
後藤 英明
私は今まで、主に血液領域のマーケティングやコマーシャルの領域で仕事をさせて頂き、新製品の市場導入準備から始まる”Product Life Cycle Management”を通して、非常に多くの「気づき」や「学び」を得る事が出来ました。
それは「常に医療のニーズや治療のゴールは変わり続けている」という事です。今日の医療は、これまでになく複雑な課題を抱えており、私たちファーマエッセンシアジャパンが自らの壁を越えてイノベーションの探求を行っているのは、これらの課題を解決する為なのです。
製薬会社の枠に囚われない発想で、医療を取り巻く社会的な問題にもアプローチしていき、多くの挑戦をして失敗から成功に結び付け、「永遠の患者志向」を実現させる事、これが私の使命です。
-

サプライチェーン本部 本部長
春名 成則
製薬業界に身を投じて以来、これまで多くの業務に携わる機会をいただきました。その都度、諸先輩方からの叱咤激励や助言を頂戴し、多くのことを学ばせていただきました。
特に、マーケティング部門に所属していた際、上司からいただいた「働いている間に、一つでも誇りに思える薬剤に巡り合えたら幸せだよ」という言葉は、今でも私の心に深く残っています。幸いにも、これまでに携わった薬剤の中に、誇りに思えるものがいくつかあり、そうした薬剤を通じて多くの方々と関わることができた経験は、私にとってかけがえのない財産です。
現在は、医薬品の品質や安全性を確保するために、各種規制を深く理解し、それを業務に適切に反映させることが求められる立場にあります。また、製品に関する重要な意思決定を行わなければならない局面にも直面することがあります。そうした場面においては、周囲の力を借りながら日々研鑽を積み、職責を全うできるよう尽力してまいります。
これまで諸先輩方から教わったこと、そして自身の経験を糧に、今後も医薬品の安定供給、品質担保、安全性確保に真摯に取り組んでまいります。